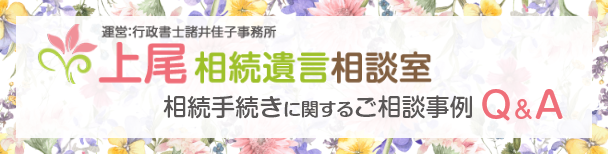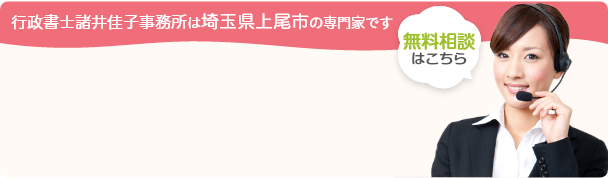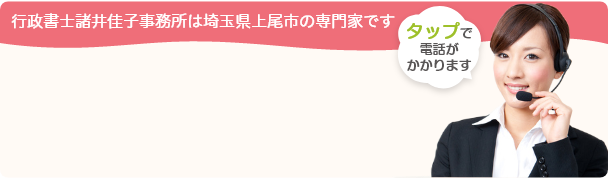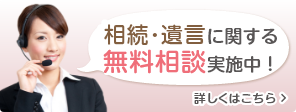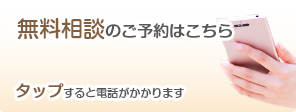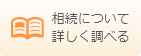2025年11月04日
Q:母名義の不動産をどのように相続すべきか悩んでいます。行政書士の先生、遺産の分割方法についてアドバイスをください。(上尾)
私は上尾在住の男性です。亡くなった母の相続について悩みがあります。
母には借金こそないものの、遺された財産はそれほど多くありませんでした。十数年前に父が亡くなって以来、母は上尾で一人暮らしをしておりましたので、老後の生活で貯金もほとんど使い切ってしまったようです。唯一価値の高い財産と言えば、母が生前に暮らしていた上尾の実家くらいです。
私には妹と弟がおりますので、相続人は3人です。この3人で遺産分割することになりますが、妹も弟も上尾を出てそれぞれ別の場所に居を構えておりますので、現実的に考えると上尾の実家は私が相続するのが妥当だろうというのが私の考えです。しかし、それでは妹と弟の相続する財産がほとんどなくなってしまいます。
行政書士の先生、家族で遺産分割について話し合うにあたり、ほかによい分割方法がないものかアドバイスを頂けないでしょうか。(上尾)
A:相続財産の分割方法として、現物分割・代償分割・換価分割の3つをご紹介します。それぞれの特徴を把握し、最適な遺産分割方法を検討しましょう。
相続財産の主な分割方法は、現物分割・代償分割・換価分割の3つがあります。それぞれのメリット・デメリットをご紹介しますので、それぞれの特徴を十分考慮し、上尾のご相談者様にとって最適な遺産分割となるよう考えていきましょう。
現物分割は、財産を売却などすることなく、現物のまま分け合い相続する方法です。今回の上尾のご相談様を例に挙げると、上尾のご実家を相続人の1人が相続し、その他の財産(預貯金など)を別の相続人が相続する、というかたちです。
【メリット】
- 相続財産を現物のまま残しておける
- 売却などの手間がかからず、相続手続きがシンプルに完了する
【デメリット】
- 各相続人の相続する財産の価値に差が生じるため、遺産分割が不公平になるリスクがある
代償分割は、一部の相続人が相続財産を現物のまま相続し、その代償としてその他の相続人に対して金銭や財産などを渡すことにより、それぞれの取得する財産額が偏らないようにする方法です。
今回の例では、まず上尾のご実家がどの程度の価値があるかを調べるために不動産評価を行い、評価額を3等分し、一人当たりが取得する金額を割り出します。そして、ご相談者様が上尾のご実家を相続し、かわりに妹様と弟様に相応の金額を支払う、という流れです。
【メリット】
- 相続財産を現物のまま残しておける
- 代償金を支払うことで、偏りのない遺産分割を目指すことができる
【デメリット】
- 相続財産を現物のまま相続した人は代償金を工面しなければならず、経済的な負担がかかる
換価分割は、相続財産を売却、現金化してから分け合う方法です。お金を分け合うことになりますので、もっとも公平に分割できる方法といえるでしょう。
【メリット】
- 現金を分け合うため、それぞれの取得金額が明確となり、遺産分割が公平になる
【デメリット】
- 相続財産を手放さなければならない
- 売却の手間など手続きが多くなる
- 売却に手数料がかかるほか、状況次第では譲渡所得税が発生する可能性もある
以上が主な遺産分割方法です。まずは専門家に上尾の実家の評価を依頼し、その価値を確認してから、どの遺産分割方法がふさわしいか話し合ってはいかがでしょうか。
地域密着型のきめ細やかなサポートをモットーとする上尾原市相続遺言相談室では、上尾の皆様の相続に関するお悩みが解消されるよう、親身にサポートさせていただきます。初回の完全無料相談では、上尾の皆様のお話を丁寧にお伺いし、個別の事情を十分に考慮したうえで最適なアドバイスをさせていただきます。上尾の皆様は、まずはお気軽に上尾原市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
相談事例を読む >>
2025年08月04日
Q:行政書士の先生、代襲相続人になったのですが、代襲相続の場合、法定相続分の割合に何か影響はありますか。(上尾)
上尾で一人暮らしをしていた叔父が、先日息を引き取りました。叔父は生涯独身で、子はおりません。叔父の両親も他界しております。
本来であれば叔父の兄弟である父と、伯母が相続人になりますが、父は叔父よりも先に亡くなっております。そのため、父に代わって私が代襲相続人となりました。結果として、相続人になるのは伯母と私の2人だけです。
叔父の相続財産は伯母と2人で分け合うことになるのですが、私は代襲相続人という立場なので、どの程度相続する権利があるのか疑問です。代襲相続の場合、法定相続分の割合に影響はあるのかどうか、教えてください。(上尾)
A:代襲相続人は相続人の権利をそのまま引き継ぐため、法定相続分の割合に影響はありません。
結論から申し上げますと、代襲相続人は、元々の相続人がもつ権利をそのまま引き継ぎますので、代襲相続人と相続人は同等の扱いとなります。したがって、法定相続分の割合も相続人と同じです。代襲相続人だからといって、法定相続分の割合が減るということは基本的にありません。
ただし、元々の相続人に子が複数いて代襲相続人が複数になった場合、元々の相続人の法定相続分を、代襲相続人の数で割ることになります。
例えば、元々の相続人の法定相続分の割合が1/2だとします。そして、子が2人いて2人が代襲相続人になる場合は、この1/2の法定相続分を代襲相続人2人で割りますので、代襲相続人1人当たりの法定相続分は1/4になる、ということです。
上尾のご相談者様の場合、相続人は伯母様とご相談者様のお2人だけとのことでしたので、お2人の相続順位と法定相続分について、民法の定めを確認しながら計算してみましょう。
(1)法定相続人と相続順位
民法では法定相続人の範囲と相続順位を以下のように定めています。
- 第一順位:子(孫) - 直系卑属
- 第二順位:父母(祖父母) - 直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹(甥、姪) - 傍系血族
※被相続人の配偶者は常に法定相続人
上位に該当者が存在する場合、下位の該当者は法定相続人ではありません。第一順位の該当者がいない時は第二順位の該当者、第二順位の該当者がいない時は第三順位の該当者と、順に相続権が移ります。
(2)法定相続分の割合
法定相続分について記載されている、民法第900条の内容を以下に抜粋します。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上を踏まえすと、まず、上尾のご相談者様も伯母様も、共に第三順位の法定相続人です。そして法定相続分は、1/2ずつ、ということになります。
なお、補足ではありますが、上尾のご相談者様のケースでは兄妹相続に加え、代襲相続も発生しています。このようなケースでは、数多くの戸籍を取り扱うことになるため、かなりの手間と時間を要すると想定されます。相続手続きは、私ども上尾原市相続遺言相談室が代行することも可能ですので、ぜひご検討ください。
上尾の皆様、初回のご相談は完全無料でお受けしておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
相談事例を読む >>
2023年11月02日
Q:行政書士の先生、遺産相続の対象となる財産が不動産しかありません。相続人同士でうまく分け合う方法はありますか?(蓮田)
先日蓮田に住む父が亡くなったので遺産相続の手続きを行いたいと思っているのですが、父が所有していた財産が不動産しかないので困っています。
遺産相続の対象となる財産は父が暮らしていた蓮田の戸建てと、蓮田の土地があります。父名義の口座の残高を調べたり蓮田の実家を片付けながら遺品整理もしたのですが、現金はほとんど残されておらず、他に遺産相続の対象になりそうな財産も見つかりませんでした。遺言書も見当たらなかったので、蓮田の実家と土地を相続人である私、妹、弟の3人でどのように分け合うか考えなければなりません。
行政書士の先生、円満な遺産相続にするためにこれら不動産を3人で分け合ういい方法はないでしょうか。(蓮田)
A:遺産相続の対象となる不動産の分割方法をご紹介します。
今回のケースは遺言書が残されていない相続ですので、蓮田のご相談者様がおっしゃる通り遺産相続の対象となる財産をどのように分け合うかを相続人同士で話し合って決める必要があります。
被相続人が亡くなったことにより、被相続人が所有していた財産は相続人の共有財産となります。亡くなったお父様の財産である蓮田のご実家と蓮田の土地は、相続人であるご相談者様、妹様、弟様の共有財産となっていますので、遺産分割協議を行い誰がどのように遺産相続するかを決めていきましょう。不動産の分割方法として、現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法をご紹介します。
(1)現物分割
財産を現物のまま(売却などせずに)分け合う方法です。誰がどの財産を遺産相続するか、相続人全員の合意を得られればその後の遺産相続手続きはスムーズに進みますが、それぞれの不動産の評価額がほぼ同じになることは少ないため、不公平が生じやすいと考えられます。
(2)代償分割
相続人の1人(または複数人)が財産を取得し、その他の相続人に対して代償金(または代償財産)を支払う方法です。この分割方法も現物分割と同様に財産を売却する必要はありません。そのため不動産を取得した相続人がそのまま住み続けたいときに有用な方法といえますが、取得した相続人は相当の代償金を準備する必要があります。
(3)換価分割
財産を売却し、それによって得た現金を相続人同士で分け合う方法です。現金で分け合うため不公平が生じることは少ないですが、遺産相続の対象不動産に住み続けたい相続人がいる場合は売却に反対される可能性もあります。また不動産売却の際は譲渡所得税など別途費用が発生しますので事前に確認が必要です。
以上が主な方法です。いずれの方法であっても、まずは蓮田のご実家と土地をそれぞれ評価し、その価値を明確にしてから遺産相続の方法を検討されてはいかがでしょうか。
遺産相続の手続きは複雑なものも多いため、ご自身で進めるのに苦労される方も多くいらっしゃいます。蓮田周辺で遺産相続について相談できる事務所をお探しの方は、ぜひ上尾原市相続遺言相談室へお問い合わせください。初回無料相談にて、蓮田の皆様のご事情を丁寧にお伺いし、ご納得のいく遺産相続となるよう行政書士がサポートさせていただきます。
相談事例を読む >>