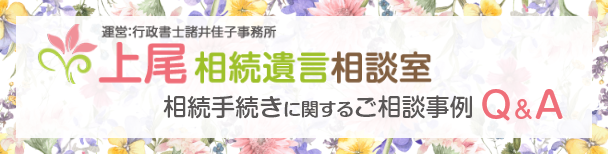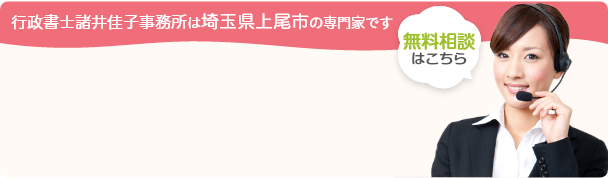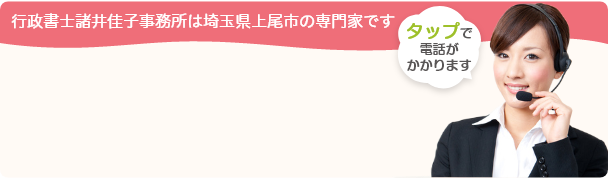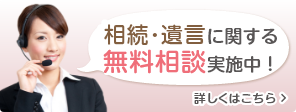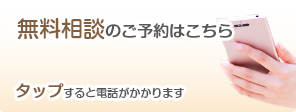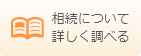2026年01月06日
Q:亡くなった母の相続手続きをしていて、必要な戸籍が分からず困っています。行政書士の先生に助けて欲しいです。(上尾)
私は上尾に住んでいる60代の主婦です。つい最近ですが、上尾の実家で一人暮らしをしていた母が亡くなったため相続手続きを行わねばならず、私がその対応を行っています。父はとっくに亡くなっており、子供も私一人のため相続手続きは私が1人で行わなければならず、非常に心細いものです。先日も、母名義のある金融機関へ自分と母の戸籍を用意して提出したのですが、これだけでは手続きは行えないという事でした。そちらの職員の方が詳しい戸籍の説明をして下さったのですが、知識がないままで聞かされても自分の理解に至りませんでした…。必要な戸籍の種類や、それらの戸籍をどうやって手に入れたらいいのか、嚙み砕いて教えていただけますか?行政書士の先生、よろしくお願いいたします。(上尾)
A:相続手続きには被相続人の出生から死亡までの戸籍および相続人の現在の戸籍が必要です。
上尾原市相続遺言相談室までお問い合わせありがとうございます。
基本的に必要となります相続手続きにおける戸籍は、「①相続人全員の現在の戸籍謄本」と、「②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」になります。ご相談者さまは、これが全て揃っていない事について指摘を受けられたものと思います。
②の被相続人の出生から死亡までの戸籍というのは、ご相談者様のお母様が誰と誰の間にいつ生まれたのか、その両親のもとでご兄弟や姉妹は何人なのか、誰と結婚して、その間に子供が何人いるのか、そしていつ亡くなったのかという情報がすべて記録として残されています。一人の方の一生において戸籍は複数に分かれていることが多いので全ての戸籍を収集する必要があります。相続手続きにおいては、お母様が亡くなったタイミングでの配偶者の有無や、過去に遡りご相談者様以外に子供や養子がいないのかを確認する必要があります。この手続きを通じて、親が認知を行っている子が判明する事もゼロではないのです。いろいろな事を考慮してお早めにすべての戸籍を取り揃えると良いでしょう。
戸籍の取得についてご案内したいのが、戸籍法の一部が改正されて2024年3月1日より開始された「戸籍の広域交付」です。この制度を利用すると本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるため、覚えておきましょう。この制度では被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が一か所の市区町村窓口で取得できるようになりました。但しこの広域交付の制度利用は、本人や配偶者、子、父母などに限られます。兄弟姉妹や、その他代理人の方は利用は出来ません。
戸籍というのは、いくつか種類があり普段なかなか目にするものではないため非常に分かりにくいと思います。相続手続きにおいては戸籍収集に始まり煩雑な様々な手続きがあります。専門の知識が求められる事も少なくないため、途中で手続きが滞ってしまい悩む方もいらっしゃいます。ご自身での手続きに少しでもご不明点やご不安がある方は、ぜひお気軽に上尾原市相続遺言相談室までご相談ください。初回完全無料相談ですので、上尾の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
相談事例を読む >>
2025年12月02日
Q:相続手続きはどのくらいの期間を要するのか行政書士の方に伺います(上尾)
上尾の父が亡くなったので相続手続きをやらなければならないのですが、高齢の母は私に任せると言って何もしようとしません。私も初めてのことですし、仕事も家庭もあって忙しく、これ以上負担を増やしたくないのが本音です。相続手続きばかりに時間をかけてはいられないので、手続きに要する期間について知りたく問合せました。教えていただけるようでしたら提出書類なども知りたいです。もちろん、貴所に伺った方がいいのであれば伺います。ちなみに、相続人は母と私の二人です。父の相続財産は、まだきちんと調べてはいませんが、上尾の自宅と預貯金が数百万円あることはわかっています。(上尾)
A:相続手続きに要する一般的なお時間と必要書類についてご説明しますが、詳しくは一度お越しください。
ご相談者様はまだ相続財産を明確にはされていないようですので、今後財産調査をされる際の参考に、相続手続きに関係する一般的な財産についてご説明します。
・現金や預金・株などの金融資産
・ご自宅の建物や土地などの不動産など
対象財産については他にも有りますので詳しくは一度上尾原市相続遺言相談室にお越しください。
こちらでは、上記2つの財産についてご説明いたします。
【金融資産のお手続き】
亡くなった方(被相続人)の口座名義を相続人名義へ変更する、または解約して相続人へ分配するためのお手続きです。
お手続きにかかる期間・・・一般的に2か月弱
必要書類・・・戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等
※各ご家庭の相続内容、ならびに金融機関によって必要書類は異なるため詳しくは各金融機関にご確認ください。
【不動産の手続き】
亡くなった方(被相続人)が所有する不動産の名義を相続人の名義へ変更するためのお手続きです。
お手続きにかかる期間・・・一般的に2か月弱
必要書類・・・戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等
必要書類を揃えて法務局で申請を行います。
上記は一般的な相続手続きに関する内容となっていますが、下記のような場合には家庭裁判所におけるお手続きも必要となるため、さらに多くのお時間を費やすことになります。
・ご自宅において自筆証書遺言が見つかった
・行方不明の相続人がいる
・未成年の相続人がいる など
相続手続きについてご不安のある上尾の方は上尾原市相続遺言相談室の専門家までご相談ください。
上尾原市相続遺言相談室では、上尾のみならず、上尾周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。上尾原市相続遺言相談室では上尾の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、上尾原市相続遺言相談室では上尾の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
上尾の皆様、ならびに上尾で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
相談事例を読む >>
2025年11月04日
Q:母名義の不動産をどのように相続すべきか悩んでいます。行政書士の先生、遺産の分割方法についてアドバイスをください。(上尾)
私は上尾在住の男性です。亡くなった母の相続について悩みがあります。
母には借金こそないものの、遺された財産はそれほど多くありませんでした。十数年前に父が亡くなって以来、母は上尾で一人暮らしをしておりましたので、老後の生活で貯金もほとんど使い切ってしまったようです。唯一価値の高い財産と言えば、母が生前に暮らしていた上尾の実家くらいです。
私には妹と弟がおりますので、相続人は3人です。この3人で遺産分割することになりますが、妹も弟も上尾を出てそれぞれ別の場所に居を構えておりますので、現実的に考えると上尾の実家は私が相続するのが妥当だろうというのが私の考えです。しかし、それでは妹と弟の相続する財産がほとんどなくなってしまいます。
行政書士の先生、家族で遺産分割について話し合うにあたり、ほかによい分割方法がないものかアドバイスを頂けないでしょうか。(上尾)
A:相続財産の分割方法として、現物分割・代償分割・換価分割の3つをご紹介します。それぞれの特徴を把握し、最適な遺産分割方法を検討しましょう。
相続財産の主な分割方法は、現物分割・代償分割・換価分割の3つがあります。それぞれのメリット・デメリットをご紹介しますので、それぞれの特徴を十分考慮し、上尾のご相談者様にとって最適な遺産分割となるよう考えていきましょう。
現物分割は、財産を売却などすることなく、現物のまま分け合い相続する方法です。今回の上尾のご相談様を例に挙げると、上尾のご実家を相続人の1人が相続し、その他の財産(預貯金など)を別の相続人が相続する、というかたちです。
【メリット】
- 相続財産を現物のまま残しておける
- 売却などの手間がかからず、相続手続きがシンプルに完了する
【デメリット】
- 各相続人の相続する財産の価値に差が生じるため、遺産分割が不公平になるリスクがある
代償分割は、一部の相続人が相続財産を現物のまま相続し、その代償としてその他の相続人に対して金銭や財産などを渡すことにより、それぞれの取得する財産額が偏らないようにする方法です。
今回の例では、まず上尾のご実家がどの程度の価値があるかを調べるために不動産評価を行い、評価額を3等分し、一人当たりが取得する金額を割り出します。そして、ご相談者様が上尾のご実家を相続し、かわりに妹様と弟様に相応の金額を支払う、という流れです。
【メリット】
- 相続財産を現物のまま残しておける
- 代償金を支払うことで、偏りのない遺産分割を目指すことができる
【デメリット】
- 相続財産を現物のまま相続した人は代償金を工面しなければならず、経済的な負担がかかる
換価分割は、相続財産を売却、現金化してから分け合う方法です。お金を分け合うことになりますので、もっとも公平に分割できる方法といえるでしょう。
【メリット】
- 現金を分け合うため、それぞれの取得金額が明確となり、遺産分割が公平になる
【デメリット】
- 相続財産を手放さなければならない
- 売却の手間など手続きが多くなる
- 売却に手数料がかかるほか、状況次第では譲渡所得税が発生する可能性もある
以上が主な遺産分割方法です。まずは専門家に上尾の実家の評価を依頼し、その価値を確認してから、どの遺産分割方法がふさわしいか話し合ってはいかがでしょうか。
地域密着型のきめ細やかなサポートをモットーとする上尾原市相続遺言相談室では、上尾の皆様の相続に関するお悩みが解消されるよう、親身にサポートさせていただきます。初回の完全無料相談では、上尾の皆様のお話を丁寧にお伺いし、個別の事情を十分に考慮したうえで最適なアドバイスをさせていただきます。上尾の皆様は、まずはお気軽に上尾原市相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
相談事例を読む >>